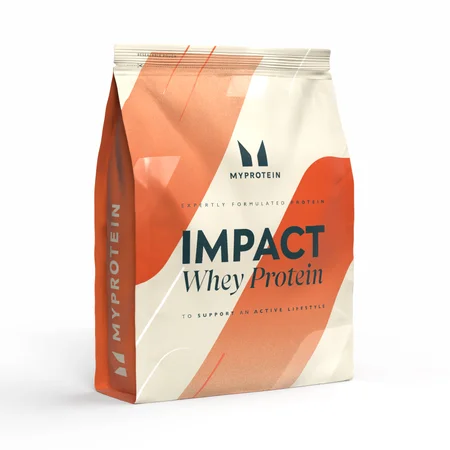PFCバランスとは?計算方法を解説!食べて痩せるダイエット

この記事で分かること:
PFCバランスとは何か

1日に必要なカロリーを知ろう
基礎代謝量の計算方法
身体活動レベル
【身体活動レベル別の活動内容】(男女共通)
| 身体活動レベル | 低い(Ⅰ) | ふつう(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) |
|
1.50 (1.40~1.60) |
1.75 (1.60~1.90) |
2.00 (1.90~2.20) |
|
| 日常生活 |
座位の仕事がほとんど 静かな活動が中心 |
仕事での移動や家事、 買い物、通勤で動く |
立ち仕事あるいは スポーツの習慣あり |
必要なカロリーの計算例
PFCバランスの計算方法
PFCバランス
| 年齢 | タンパク質 |
脂質 (飽和脂肪酸) |
炭水化物 |
| 18~64(歳) | 13~20% |
20~30% (7%以下) |
50~65% |
PFCバランスの計算
PFCバランスの取れた献立&メニュー

※栄養成分参照:文部科学省食品成分データベース
エネルギー2698kcal
タンパク質135g
脂質90g
炭水化物337g
【朝】
エネルギー871kcal
タンパク質32.2g
脂質29.7g
炭水化物114.3g
【昼】
エネルギー882kcal
タンパク質44.6g
脂質26.1g
炭水化物113.7g
【間食】
エネルギー151kcal
タンパク質5.3g
脂質3.7g
炭水化物26.2g
【夕】
エネルギー782kcal
タンパク質53.1g
脂質29.1g
炭水化物71.8g
エネルギー2686kcal
タンパク質135.2g
脂質88.6g
炭水化物326g

筋トレの効果UP!筋トレ前の食事TOP10
ダイエット中の脂質の取り方
MCTオイル
えごま油
オリーブオイル
まとめ

管理栄養士兼ライター。総合病院・企業を経てフリーランス管理栄養士として独立。主に Web サイトの記事執筆を行い、根拠に基づいた栄養情報の発信を行う。学生時代は陸上、社会人からはハーフマラソンに取り組み、産後も体力づくりに励む。
エネルギー産生栄養素バランスは、 (n.d.). -5 エネルギー産生栄養素バランス 1 基本的事項. [online] Available at: https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586560.pdf.
日本人の食事摂取基準2020年 Ⅱ 各論1 エネルギー・栄養素 エネルギー [online] Available at: https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586556.pdf
日本人の食事摂取基準2020年 Ⅱ 各論1 エネルギー・栄養素 エネルギー [online] Available at:
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586556.pdf
MCT オイル (MCT Oil). (n.d.). [online] Available at: https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk/66/11/66_440/_pdf/-char/ja
中鎖脂肪酸の栄養学的研究一最近の研究を中心に (n.d.). [online] Available at:―https://www.jstage.jst.go.jp/article/oleoscience/3/8/3_403/_pdf
What is MCT | 日清オイリオ. (2022). What is MCT | 日清オイリオ. [online] Available at: https://www.nisshin-oillio.com/mct/
ジェトロ. (2022). えごま | 日本産食材ピックアップ – 農林水産物・食品の輸出支援ポータル. [online] Available at: https://www.jetro.go.jp/agriportal/pickup/egoma.html
e-ヘルスネット 情報提供. (2022). 不飽和脂肪酸. [online] Available at: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-031.html
オリーブオイル 東京聖栄大学健康栄養学部食品学科食品衛生学研究室. (n.d.). [online] Available at: https://www.tsc-05.ac.jp/images/nutrition_ed/2018fsp/04.pdf