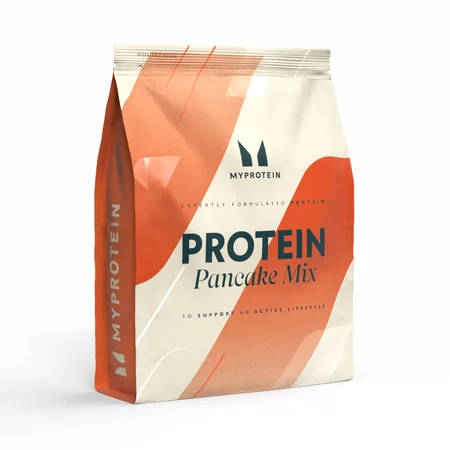チートデイとは?やり方や頻度・周期、おすすめの食べ物を解説!

この記事で分かること:
1. チートデイとは?2. チートデイを行うメリット3. チートデイのやり方と摂取カロリーの目安4.チートデイの頻度・周期5.チートデイの注意点6.まとめ
チートデイとは?
チートデイを行うメリット
停滞期解消
不足しがちな栄養素の補給
ストレス解消
チートデイのやり方と摂取カロリーの目安
チートデイのやり方
チートデイの摂取カロリーの目安
チートデイに食べるものは?

チートデイにおすすめの食べ物

チートデイの頻度・周期
①ダイエット停滞期に行う
②体脂肪率から頻度を決める
| 男性(体脂肪率%) | 女性(体脂肪率%) | チートデイの頻度 |
| 15%~20% | 25%~30% | 2週間に1回 |
| 10%~15% | 20%~25% | 10日に1回 |
| 10%以下 | 20%以下 | 1週間に1回 |
③BMIから頻度を決める
| BMI | チートデイの頻度 |
| 23~25 | 1ヶ月に1回 |
| 22~23 | 3週間に1回 |
| 20~22 | 2週間に1回 |
| 20以下 | 1週間に1回 |
チートデイの注意点
チートデイを単なる食べ放題の日にしない

チートデイ以外の日は食事内容を整える
ご褒美目的や無計画なチートデイを設定しない
まとめ

PFCバランスとは?計算方法を解説!食べて痩せるダイエット

筋トレの効果UP!筋トレ前の食事TOP10

【プロ直伝】筋トレのモチベーションを上げる8つの方法

管理栄養士兼ライター。総合病院・企業を経てフリーランス管理栄養士として独立。主に Web サイトの記事執筆を行い、根拠に基づいた栄養情報の発信を行う。学生時代は陸上、社会人からはハーフマラソンに取り組み、産後も体力づくりに励む。
Escalante, G., Campbell, B.I. and Norton, L. (2020). Effectiveness of Diet Refeeds and Diet Breaks as a Precontest Strategy. Strength & Conditioning Journal, Publish Ahead of Print. doi:10.1519/ssc.0000000000000546.
江澤 郁子 (2001). 間違ったダイエットの骨への影響. 日本家政学会誌, [online] 52(10), pp.1029–1034. doi:10.11428/jhej1987.52.1029.
ダイエット行動の三日坊主に対する予防・教育的プログラムの実証的研究, [online] Available at: https://otani.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=33&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1.
Johas.go.jp. (2020). 2020年9月号『コロナ太りはストレス太り!心と体ががんばっている証拠です。』 | 茨城産業保健総合支援センター. [online] Available at: https://ibarakis.johas.go.jp/archives/13843
e-ヘルスネット 情報提供. (2019). 身体活動とエネルギー代謝. [online] Available at: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-02-003.html
戎 利光 (1999). 健康科学講座-朝食抜きや過激なダイエットによる悪影響-. 福井大学教育学部総合自然教育センター年報, [online] 2, pp.54–57. Available at: https://u-fukui.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=23282&item_no=1&page_id=13&block_id=21
e-ヘルスネット 情報提供. (2017). 肥満と健康. [online] Available at: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-02-001.html
e-ヘルスネット 情報提供. (2018). 体重コントロール. [online] Available at: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-06-008.html
e-ヘルスネット 情報提供. (2022). 体脂肪率. [online] Available at: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-041.html
e-ヘルスネット 情報提供. (2019). ダイエット. [online] Available at: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-090.html
ダイエットコントロール中の過食により急性胃拡張を呈した一例, [online] Available at: https://tmu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=5605&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1.