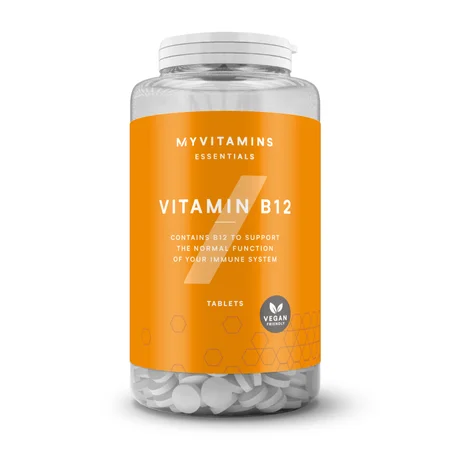食事でハッピーになる5つの方法|気持ちのアップが期待できるムードフード

今後の金銭面について心配がある。自分が考えた通りには仕事がうまくすすまない。自分の前を歩く人のスピードがいらいらするほど遅い。あなたにストレスを与えるものがなんであれ、一人で抱え込むのはやめましょう。何か解決手段はあるものです。
実際、私達の3分の2のあたる人々がストレスに起因するメンタルヘルスの問題を抱えている(or 将来経験する)という調査結果があります。
では、メンタルヘルスの問題を防ぐには何ができるでしょうか?あなたの上司の人格を変えることはできませんが(できたらいいのですが)、日々の生活であなたがコントロールできるものはあります。例えば、食べる物を選ぶこと等です。
目次:
良い食事で、良い気持ちに
栄養の欠乏と体の病気の関係性を理解することは難しくありませんが、食事とメンタルヘルスの結びつきを理解している人は殆どいません。研究者はこれまでの調査の結果、気持ちの状態と食べた物には関係性があるということが分かっており、それらの関係性は脳腸軸と呼ばれています。
栄養を正しく摂取することで、長期的にはメンタルヘルスをサポートすることができます。今回は、皆さんが健康的な食事を摂ることができるように、科学的調査に裏付けされたストレスを吹き飛ばす食事のコツを5つご紹介します。

1. オメガ脂肪酸
EPA、DHAといった魚油に含まれるオメガ3脂肪酸は健康に良いということに加え、気分にもポジティブな影響があることが分かっています。EPA及びDHAは神経シグナルに影響を及ぼすからなどと考えられています。
オメガ3脂肪酸はどうしたら摂取できる?
脂肪の多い魚類やサプリメント、植物性オメガ(えごま油、亜麻仁油など)などからEPAとDHAを摂取しましょう。1.5~2gのEPA摂取により気分が上向きになることが科学的調査の結果分かっています。
2. ビタミンB群、葉酸とビタミンB12
長期間に渡ってビタミンB群、葉酸とビタミンB12を摂取することで気持ちに良い影響があることが研究の結果分かっています。葉酸とビタミンB12は神経機能にとって重要なS-アデノシルメチオニン(SAM)の代謝作用に関係しているからだと考えられています。
葉酸とビタミンB12は何に含まれる?
葉酸は果物や野菜、全粒穀物、豆、シリアル、強化小麦などの穀物、穀物製品など幅広い食品に含まれています。但し、通常の食事だけで十分な量の葉酸を摂取することは簡単ではありません。
葉酸と同様にビタミンB12も、動物性食品、栄養強化シリアル、栄養添加豆乳もしくはライスミルクなど幅広い食品に含まれています。但し、一部の人々でビタミンB12を適切に消化吸収できないリスクのある方がいらっしゃいます。例えば50代以上の10~30%は十分な胃酸がなく十分吸収することができません。また、動物性食品を食べない人々についてはビタミンB12を摂取することで栄養を補完することが推奨されます。

3. 炭水化物
これは恐らく聞き慣れた情報ではないと思いますが、炭水化物は必ずしも悪者というわけではありません。事実、ローカーボダイエットを取り組んでいる人を見れば分かる通り、炭水化物は気分や振る舞いに影響を及ぼすことが知られています。
炭水化物の消費は脳内へのトリプトファン供給につながり、その結果、安心や満足感を増加させることになるからです。
どんな炭水化物が良いのでしょう?
GI値の低い全粒穀物や野菜はムードに継続的な影響をもたらすことが分かっています。GI値の高い砂糖を用いたスイーツ類、精白パンなどの加工食品による影響は一時的なものにしかなりません。
4. タンパク質
タンパク質は健康的な食事にとって欠かすことのできない栄養素ですが、タンパク質は気持ちのメンテナンスにとっても重要であることにお気付きでしょうか。
アミノ酸はタンパク質の成分となっており、脳の機能及びメンタルヘルスにとって不可欠な多くの神経伝達物質はアミノ酸から作られています。例えば、ドーパミンはアミノ酸とチロシンから作られており、ドーパミンの不足により気分の落ち込みや攻撃的になることにつながります。
タンパク質はどう摂取したらよいですか?
高品質なタンパク質を含む肉、魚、その他動物性食品(卵や牛乳)などから9種類の必須アミノ酸を摂取することが重要です。
もしあなたがベジタリアン、または動物性食品の食べる量を減らしている場合、マメ科植物、大豆、ナッツ、種、植物性タンパク質、豆腐などから摂取することができます。植物性の食品の場合、特定の種類のアミノ酸含有量が少ない場合がありますので、多くの種類の食品からタンパク質を摂取することが重要です。
5. 亜鉛
不可欠な微量栄養素である亜鉛は、からだの構成要素の成長や代謝、体のリズムや活動、外部からの防御を助ける多くの役割を担っています。
体内の亜鉛が低いレベルにあると落ち込みにつながり、口腔からの亜鉛摂取はセラピー結果に影響があることが研究で分かっています。
亜鉛はどう摂取すればよい?
肉、魚、牛乳、チーズ、種、ドライビーンズ、エンドウ豆、レンティル豆は亜鉛を多く含んでおり、食事に簡単に取り込むことができます。
本記事は情報提供および知識向上を意図としたものであり、専門的な医療アドバイスを目的としたものではありません。ご自身の健康に何か懸念がある場合は、健康食品を摂取する前もしくは食習慣を変更する前に、専門医やかかりつけの医療機関にご相談ください。

ジェニファー・ブロウ(Jennifer Blow)はマイプロテインの編集者で、UKVRN*登録の栄養士としてキャリアを始めたばかり。栄養科学の学士号と栄養学の修士号を保有。現在は、スポーツサプリメントの健康・フィットネスへの使用について、科学的根拠に基づいた調査・研究を行なっています。*UKVRN:英国における栄養士の登記簿。登録には高い専門性と能力が必要。
また、エクササイズや健康的なライフスタイルのための栄養科学を専門としていることから、ヴォーグ、エル、グラツィアなどの有名オンライン雑誌に栄養士として登場しています。
これまで、NHS(イギリスの国民保健サービス)と協同で食生活への介入研究を行ったり、オメガ3脂肪酸サプリメントについてや、ファストフードが健康に及ぼす影響についての学術研究など、幅広い経験を積んできました。特に後者に関しては、毎年開催されるNutrition Society Conferenceで発表も行いました。さらに、プロ養成のために開催されるイベントにも多く出席し、常に高い専門性を維持しようと努めています。
ジェニファーについて詳細は、こちらをご覧ください。
プライベートでは、ヒルウォーキングとサイクリングの愛好家。SNSを通じて、我慢しなくても健康的な食生活が送れることを広めています。